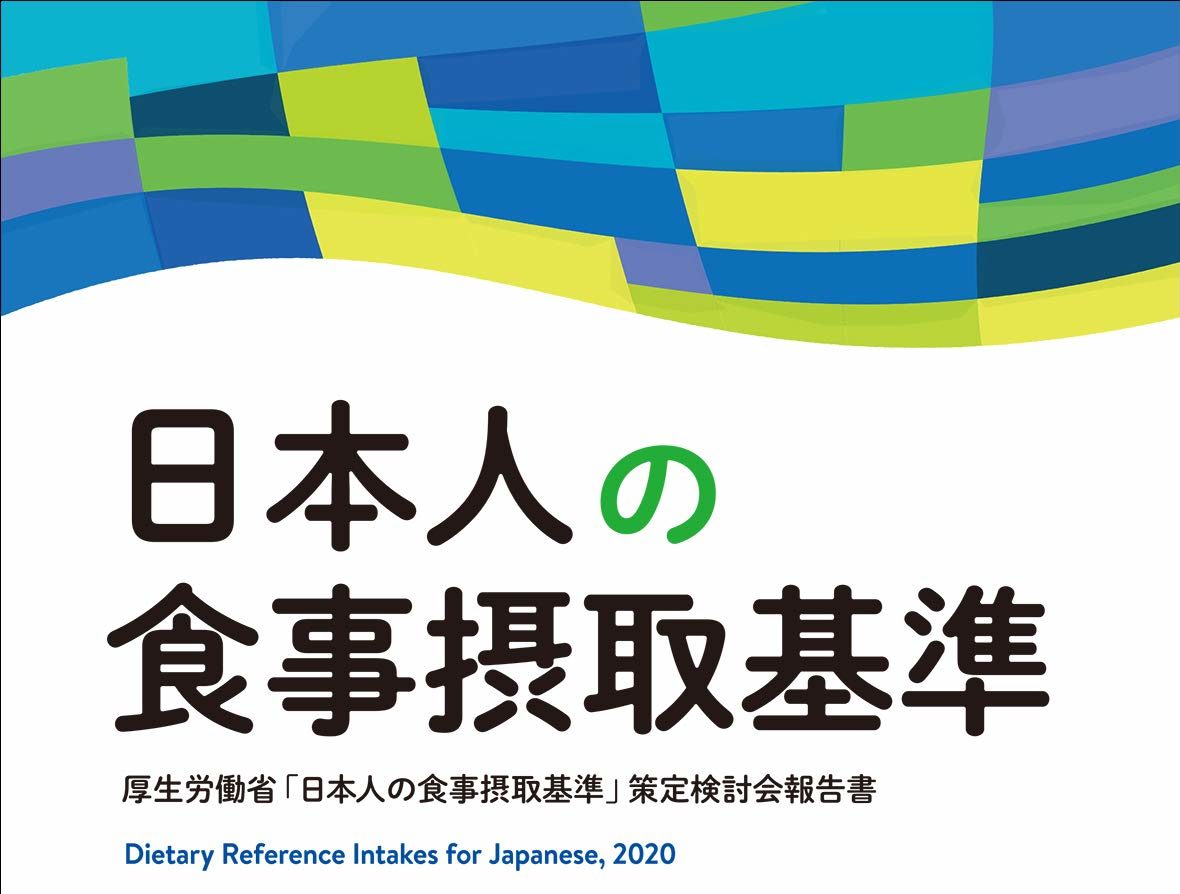栄養サポートチームは、医師、管理栄養士、看護師、薬剤師、理学療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床検査技師などから構成される栄養管理の専門のチームです。
管理栄養士は栄養サポートチームでは中心的存在となります。
食事のことはもちろんですが、経腸栄養剤や濃厚流動食、輸液内容から、各種疾患の病態に関する知識から薬剤に関する範囲まで幅広い知識が求められます。
また専従の場合は、チームをまとめるという役割もあるため、調整能力やコミュニケーション能力を求められる場面が非常に多いです。さらに、プレゼンテーションをする機会も多いため、いろいろな意味で力を試されるのがNST専従者の仕事となります。
どうすればなれるのか
まず、NSTが稼動している病院に管理栄養士として就職する必要があります。最近でしたら中核病院以上であれば、大体どの施設もNSTが稼動していると思います。
大学病院や、国立病院、自治体病院(県立病院、市民病院)くらいでしたら問題ないでしょう。
しかしレベルにはばらつきがあります。本腰を入れ、活動しているところもあれば、形だけなんとなくのチームとして活動しているところもあります。
どこの病院へ就職するか
NSTが稼動している病院に就職したとしても、すでにNSTに従事している菅理栄養士がいるわけですので、基本的にはポストが空くまで待つしかないとことが現実です。
したがってなりたいからなれるものでもなく、運も大きな要因であるということは覚えておいてください。(管理栄養士としての実力や信用はいわずもがなです)
NSTメンバーになるための条件
またNST専従者として、NSTのメンバーで活動し、診療報酬を取得するには要件があります。別途定める40時間の研修を受ける必要性があります。よくある勘違いとして、NST専門療法士を取得しないと算定が出来ないと考えているケースもありますが、NST専門療法士は単なる学会認定資格であり、算定報酬の要件ではありません。
つまり、特定の施設で、指定された40時間の研修さえ受ければ、誰でも診療報酬の加算を取ることができるのです。
ここは自施設の上司に相談しましょう。個人で受けるわけでなく、組織として派遣してもらう必要性があります。
仕事内容
①基本的に、栄養サポートチームに介入している患者の栄養管理が主業務となります。
また介入していない患者でも、必要であらば、病棟に介入依頼をして頂くよう提案したり、医師からの栄養管理についての質問に積極的に答えることもNST専従者の仕事です。
②通常の業務は、介入患者の栄養管理、例えば喫食量から摂取エネルギーの把握、経腸栄養をしている患者であれば、経腸栄養に伴う副作用、下痢や逆流などないか、腹部症状がないか、熱発していないか、口腔状況などはどうかと、栄養管理に関わる問題となりうる項目のモニタリングをします。
③また必要時には栄養療法や栄養管理について本人やご家族に報告したり、転院する場合は転院先へこれまでの経緯を説明した栄養治療実施報告書を送付したり、やることはてんこ盛りです。
④また、栄養サポートチームの管理栄養士は知識のアップデートや情報発信をするべきであり、年に1度の学会発表も必要です。定期的に学術論文を投稿している管理栄養士もいます。
 管理栄養士
管理栄養士 また院内における栄養管理の啓蒙活動もとても大事な仕事の一つであり、私は毎月1回NST通信というものを作成し、全職員が閲覧できるようメール送信していました。
⑤週に1度の回診日は、1日中回診及びカンファレンス、またその準備に時間を費やします。
⑥病院によって様々ですが、基本的には医師がメンバーの意見を統括し、チームとしての提案をします。専従管理栄養士は、そのチームとしての提案を、メンバー代表として、栄養治療実施計画及び報告書に記載をして、主治医に提案します。
⑦1回の回診で算定を取ることができるのは30人までですので、施設や状況にもよりますが、最大30人の報告書を作成する必要性があります。いかに効率良く業務できるかが鍵となってきます。




私は回診カンファレンス日の前日に、あらかじめ栄養治療実施計画書兼報告書を大まかに作成しておきました。当日、変更がある場所だけ、記載し直すことによって負担が軽くなるようにしました。
勤務時間
定刻通りの勤務時間となります。
私の場合は8:30~17:15でした。(1時間休憩を含む)
休日
施設にもよりますが、暦通りです。有給は年20日ありますが、チームの調整役といった立場のため、正直自由に有給を取りにくいというのが現実です。
給与
施設に準じます。NST専従だからといって他の管理栄養士より高くなることはありません。
NSTに携わるのにおすすめの大学




実際は大学云々より、卒後いかに学習が続けられるかが大切です。しかしながら、卒業後母校と連絡を取ることもありますし、大学同期のレベルが高い方が、卒後色々役立ちます。
偏差値は大学の善し悪しを計るツールではありませんが、偏差値の高い大学のほうが全体としてもみた場合学生の質が高い傾向にあります。
また、学会参加や論文執筆まで考えると、学位は修士以上を持っている方が有利でスムーズですので余裕や意欲があれば大学院進学まで視野にいれてみてはいかがでしょうか。